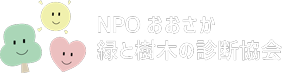樹木医アラカルト
藪医の日記より(チャドクガについて)
樹木や草花を観察したり、生育診断をしたメモをめくりながら、書いたものです。 今年の夏、猛暑が続く折、近所の樹木診断を行っていて、チャドクガの毒刺にやられた、いやな事を思い出し、その発生の観察メモをまとめてみました。 チャドクガの発生状況については、数年前からフェロモントラップ*1を用いて観察してきました。その発生は年により変化があり、また夏と秋では成虫(蛾)の体色が違う面白さがあります。今年の夏はほとんど黒褐色で、秋は黄褐色でした。秋の観察で朝調査板を覗くと発生量が多かったときは、調査板が黄金色に輝いて見えることがあり、調査の一つの楽しみとなっていました。 発生状況は教科書で示されているタイプと異なる場合が多いことに驚かされます。 今年はトラップ周辺のツバキ、サザンカ、チャ、に幼虫(毛虫)の発生が見られなかったにもかかわらず、昨年に比べ1化期*2(6月~8月)、2化期(10月~11月)とも蛾の発生量が多いことです。 観察状況(補殺累計) 1化期(昨年170)(今年230) 2化期(昨年60) (今年220) [...]
大阪府でもナラ枯れが拡がっています。その2
アラカシは穿孔被害を受けても枯れにくく発見が難しいため、継続的にカシナガの発生源となっています。これは他の樹種は穿孔が辺材で止まってしまうものが、アラカシの場合は心材まで穿孔できるため「心材化」が進みにくく、枯死しにくいものと考えられています。 カシナガは非常に社会性を持った昆虫で、キクイムシのなかまの中では菌食性キクイムシと呼んでいて、雌の背中には菌を運搬する特殊な器官を持っています。 また、カシナガは糸状菌(カビ)を媒介し、それを食べていると言われていますが、実際に食べているのは酵母で、カビで樹木を殺して、酵母を栽培し、酵母を食べていることが観察で確認されています。 生活環は春先にまず雄が衰弱木を見つけて穿孔します。そして、フェロモンで雌を呼び寄せます。(集合フェロモンで、同じ木に他の雄も呼び寄せます) 雌はオスのあけた穴に入ってくるとき鳴き声を出しますが、オスはこの声で同種の雌であることを確認して、カップルになります。そしてすぐに交尾し産卵し孵化した幼虫はワーカー(働き手)として、親の手伝いをします。 たとえば、カビや酵母を孔道内で移動させたり、母親の生んだ卵を孔道の奥に運んだり、また、乳液を分泌して、幼虫同士で栄養を交換しあったり、発達の遅い幼虫を大きくなった幼虫が助けたりするそうです。(何と家族愛にあふれた虫だろうか。それに比べて我が家は……………。) このようにして、1つの孔の一家(核家族)で1年間に500から600の成虫が増産され、1本の木に100孔があれば単純計算すれば50,000から60,000の虫が発生することになります。(何と多産であることか。) 羽化は6月ごろから始まり、6月下旬から7月がピークで、10月ごろまで続きますが、フラス(穿孔から排出されるおがくず)の発生もそのころがいちばん多いようです。そして冬季は穿孔内部で成虫で越冬します。 カシナガの駆除については、秋から冬にかけて侵入した被害木に樹幹注入をするか、被害木を伐採しシートを被せてくん蒸する方法などがあります。 予防としては、樹皮に粘着剤を塗布したり、幹にシートを巻くなどの方法がありますが、手間と費用のかかる山間部では、なかなか実施が困難なのが現状です。 吹田市の万博公園でも今年、被害が確認されていますし、今後は街中でも被害が拡がる可能性があるので、注意して見守る必要があると思います。 真田 俊秀
大阪府でもナラ枯れが拡がっています。その1
ナラ枯れは、マツ枯れとともに現在、日本の森林の2大伝染病となっています。近年、近隣の京都府等でナラ枯れの被害発生と拡大が問題となっていますが、大阪府でもH21夏に高槻市において初めて被害が確認され、今年は島本町や吹田市、枚方市、交野市などに被害が拡大しています。また全国では26府県で被害が確認されています。 このナラ枯れとは、大きさ5㍉程度のカシノナガキクイムシ(以下、カシナガ)が、産卵のため木に1~2㍉の穴をあけ入り込む際、持ち込む糸状菌(カビ)が原因で木の内部で水を通す管が目詰まりを起こし枯死する現象です。 詳しく述べると穿孔を受けた樹木は、カビの拡大を防御するために抗菌物質を生成し、辺材部も茶色く心材化しますが、心材は通水性がないので、四方八方から大量に攻撃(マスアタック)を受けると、辺材部が一気に心材化し、樹幹の通水性がなくなり、そのため一気に枯死することになるわけです。 カシナガの被害対象樹種はブナを除くブナ科に属する樹種がほとんどで、被害を受けやすい順は、ミズナラ>コナラ>クヌギの順で、常緑樹ではコジイやマテバシイが被害を受けやすいようです。 そして現在、大阪府でカシナガによる被害が出ているのは、ほとんどが大径木のコナラです。
ホームページをopenしました!
NPOおおさか緑と樹木の診断協会のホームページにアクセス頂きありがとうございます 本日2010年11月15日から、本格運用を開始いたします。 ブログを中心として、樹木医の目線で様々な活動や情報を提供していきたいと 思っております。 どうぞ、お楽しみください♪
樹木医について
樹木の診断及び治療、後継樹の保護育成並びに樹木保護に関する知識の普及及び指導を行う専門家です。 樹木医になるには、(財)日本緑化センターが実施する樹木医研修を受講して、資格審査に合格し、樹木医として登録されることが必要です。 樹木医認定者総数は平成28年12月現在で、2,673名です。 […]