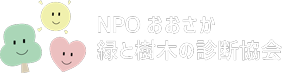樹木医アラカルト
大クスの枯死
茨木市の安威に須賀神社という神社があります。 その神社の御神木としてクスノキが崇められております。 樹高27m、枝張り25m、幹周6.8mという非常に立派なクスノキで、 大阪府の天然記念物にも指定されております。 このクスノキに十数年まえ頃から少しづつ枝枯れが増えてきて、 2年前には参拝者に危険だという事で枯れ枝の撤去がほどこされました。 この頃の幹を見てみると、幹周の1/3位の皮が剥げ落ち、 幹も半分くらい生気が見られませんでした。 最近、このクスノキを見に行くと、まったく精気がありません。 [...]
天野山金剛寺から和泉へ
桜の咲く季節になりました。 今日は大阪府河内長野市にある天野山金剛寺へやってきました。 このお寺は女人高野とも呼ばれてます。 ここは緑の多いお寺で、春の桜、秋の紅葉が美しく、また、大阪府指定文化財の杉の大木もあります。 なんとも場違いな体育館の様なものが見えてびっくりします。 これはお堂の工事のための建物のようです。 工事中とは残念ですが、樹木を見ることはできそうです。塀の向こうに満開の枝垂桜が見えますね。 [...]
東北地方太平洋沖地震で被災されたみなさまへ
東北地方太平洋沖地震で被災されたみなさまに心よりお見舞い申し上げます。 被災地の一日も早い復興を心から祈念いたします。
正しい剪定ではありませんが・・・
枝の正しい剪定は幹と枝の接合部の上に現れる皺状の構造と枝瘤を残す切り方(ナチュラルターゲットカット)が良いことはShigoがCODITモデルを提唱し、現在基本的に支持されています。 そして逆に正しくない剪定は幹に平行に深く切り落とす切り方(フラッシュカット)や枝を切り残した切り方(スタブカット)といわれています。 植物の傷口をふさぎ防御層を十分につくることを主眼におけばこれは正しいでしょうが、そこに他の生き物が絡んでくるとそうともいえない場合があります。 この写真は枝が枯れて折れてしまったか、剪定時に残された枝があったイチョウの木で、その残された枝にキツツキの一種のコゲラが営巣しているところです。(東京都港区にて) 都会の真ん中にもかかわらず、このような野鳥が生息できるのは残された枯れ枝のおかげと言えるでしょう。 [...]
ソテツの種子と発芽
ソテツの種と言うとあまりなじみがないかもしれませんが、昔は、表面を加工してサルの人形として縁日などで 売られているのをよく見かけました。朱色が際立っていたのが懐かしい思い出です。ところが今は、種子の心皮が 悪魔の羽としてインターネットで売られているのを知り、なんでも売れるものだと時代の変化に驚いています。 ところで、ソテツの種から出芽するところはなかなか見る機会が少ないと思います。 普通、植物は種子の片方から芽をだし、その反対側から根を出して成長していきます。 ところがソテツは、種子から先ず芽株を作ります。その芽株から出芽し、根を出して成長していきます。傾いた ソテツに芽株が多いのは、幹が倒れた時に少しでも早く芽を吹く為の準備かもしれませんね。 [...]
今日は落葉果樹のせん定のお話です。
果樹のせん定でまず覚えることは「切返せん定」と「間引きせん定」です。 「切返せん定」は図1のようなせん定で、1年生の枝をその途中から切るせん定です。切返をすると、春には元気のよい新しい枝がたくさん伸びます。 「間引きせん定」は図2のようなせん定で、1年生の枝を元から間引くせん定です。 枝が間引かれため、その部分には伸びる芽がないので、全体として枝の発生が少なくなります。 樹が大きくなって困るときに不用意に切り返すと、逆に元気な枝がたくさん出て、せん定前より大きくなってしまうことがよくあります。 樹をコンパクトにしたいときは間引きせん定中心にせん定をすることがポイントとなります。 次に、果樹のせん定で大事なことは、花の着き方を覚えることです。 果樹の種類によって花の着き方が違い、それに応じたせん定が必要になります。 図3と図4はせん定後の花の着き方を模式的に表したものです。 左側がせん定の時の状態、右側がせん定後、芽が伸び、開花したときの様子です。 図3のタイプはうめ、もも、すももなどの花の着き方です。前年の枝に花が着き、果実となります。 [...]