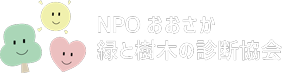樹木医アラカルト
剪定バサミと剪定された断面
樹木を切る時に使われる道具、となりますと刃物ですが、刃物には大きく分けて3種類あります。一つはナイフのように切るもの。もう一つはノコギリやヤスリのように、基本的には削るもの。そして、全く別の作用を利用するハサミ。 ハサミは切れる!という印象がとても強いのですが、実際のところカッターナイフや小刀のように鋭利ではありません。仮にハサミを手に持って、その片方の刃で木を削っても、とても小刀やナイフのような切れ味は、さっぱりありません。 しかし木の枝を切るには、やっぱりハサミが必要です。アートナイフのように極めて鋭利な刃物なら、より硬い枝がスパスパ切れるんじゃないかなと思うのですが、現実は全く反対でナイフなどではせいぜい挿し木や接木の小枝を切るのがやっとなのです。 太い枝・硬い枝を切るとなりますと、そこは剪定バサミの登場です。 剪定バサミを観察しますと、片方の刃は“刃”とはとても言えない受け刃(ほぼ、ただの角を持った金属板)になっており、片方は大きな刃となっています。 これは実に不思議です。片方は刃らしい刃がないのに、しかし大きな枝が切れる。ナイフのようなもっと鋭利な刃ものでは切れないのに・・・です。しかしこれこそが鋏の芸術的な構造、機構なのです。単にテコの原理でどうこうという訳でもありません。(テコの原理だけですとペンチやヤットコのような機構になりますが、それではもぎってちぎるような結果になります。) ハサミとは、ある一点にだけ力が集約することで、対象を切断するという素晴らしい仕組みを持った芸術品であり、いかに一点に力を余さずそらさず集約するかということについて、例えばそりやすきなどの技法が追求され、刀の技法と同様に軟鉄と鋼鉄の層構造さえも飲み込み、新たにバナジウム鋼やステンレスなどの合金までも貪欲に取り入れつつ、カッターやナイフとは全く異なり、剪断応力を引き出すため今尚進化しつづける精密機械なのです。 [...]
大阪南港の貯木池
ここは大阪府柏原市です。奈良から大阪へ流れてきた大和川と、大阪南部から北へ流れてきた石川が、ここ柏原市役所の前で合流します。合流した大和川は西へ流れて大阪湾へ続いています。 この大和川の合流地点の堤防上を西へ(大阪湾の方へ)続く道があります。見晴らしが良く気持ちの良い道です。この道は自動車の通行が禁止されてるため、安心してウォーキングやサイクリングができます。ここから大和川の河口までは、このような気持ちの良い道と一般道を行き来しながら、距離にして20km程です。20kmといえばウォーキングには距離が長すぎますが、サイクリングなら速い人で1時間程度、のんびり進んでも1時間半くらいで行けそうです。道は平坦でアップダウンはほとんどなく、ほぼ一本道の容易な道です。 今日はいい天気ですから、この道を河口の辺りまでサイクリングしてみましょう。それでは出発します。 [...]
樹木巡礼 ブログ版 ②
プロゴルファー宮里藍さんの故郷、沖縄県東村(ひ がしそん)の道の駅でマンゴーカステラとパイナップ ルのポン酢(沖縄本島の北部の土壌は強烈な赤土でP Hは4ぐらいでパイナップルが特産です)を買って、 村役場で地図をもらい車で走ること約10分、そぼ降 る南国の雨の中ひと気のない川沿いの森に包まれるよ うに、板根は優美な曲線を描いています、樹の持つ環 [...]
藪医の日記より(アレロパシーについて)
庭に野良猫が入ってきて困ったとき、その対策で猫の忌避剤を使ったことがありましたが、有効性は感じられませんでした。その後、柑橘類の皮とコーヒーの濾し殻を猫が嫌がることを聞いて、それを庭に撒いて猫を遠ざけることを試みました。 柑橘類の皮は効いたように思いましたが、コーヒーの方ははっきりしませんでした。しかし、コーヒーの濾し殻を撒いた場所に雑草が少ないことに気がつきました。しばらくすると、雑草ばかりでなく植木にも影響が出てきたので使用を辞めた経過があります。この作用がアレロパシー(他感作用)であるいうことが分かり、専門書を調べるとアレロパシーは、数多くの植物でも確認されていて、その利用の研究もなされています。 また植物の遷移でも調査されていて、ヨモギ属がカラムギ、ハマチャヒキを排除して、灌木形成をしている現象が知られています。 樹木ではアカマツの下で、イヌタデ、ハキダメギクの生育が悪くなる現象が確認されています。ナギは生育が大変遅い植物ですが、その樹林で下草が生えない報告があります。奈良の春日大社の裏山のナギ樹林で、この作用が確認されています。その他、街路樹にも植栽されているタマリンドは、その樹下でテントを張ると、テントの布がぼろぼろになるという報告がありますが、この作用は葉から出る有機酸が原因で起こり、その下に生える雑草も抑えられています。 アレロパシーは植物の病原菌の生育抑制や殺菌作用を示すことも研究されており、古くから農法で輪作、間作、混植が行われています。具体的にはコンニャク畑にエンバク、ユーガオ畑にネギの混植でコンニャクの乾腐病、ユウガオの土壌病害が抑制されることがあります。 庭で経験したコーヒーによる雑草への作用は、コーヒーに含まれているカフェインがハリビユ、カラスムギ、イヌビユの発芽抑制に働いたアレロパシー(他感作用)でした。 自然の働きに驚きと、面白さを知った次第です。樹木や庭の草花を扱っていると多くの不思議な現象を見ることができるので、今後も注意深く観察していこうと思っています。 T O 生
台湾のクスノキ巨木治療痕から
現在(1月20日)台湾に来ています。1月16日早朝、氷が張る寒い大阪を震えながら出発し、暖かい台湾に向かいました。 ところが台北の空港から表に出れば大阪と変わらない気温。今年の台湾は寒い日が非常に多いとの話です。薄着しか持ってきておらず、早々に防寒用作業ジャンバーを購入する羽目になってしまいました。 今回の台湾出張は、宜蘭縣と台中縣を主体に回りました。宜蘭の街から山を見ると雪化粧しているではありませんか。宜蘭では二日間土壌調査を実施し、それから台中に向かいました。台中では20度をこえる気温になり購入したジャンバーが邪魔になる始末です。九州とほぼ一緒の面積という狭い国ながら、山の上では温帯、北部の平地は亜熱帯、南部の平地は熱帯と変化に富んだ気候帯を持ち合わせる国です。 台中縣では豊原市というところで、「澤民樹」と命名された樹齢1000年を超えると言われる大きなクスノキを見てきました。2本のクスノキが根元部で癒合し、数匹の大蛇がうねったような独特な樹形をしています。葉が少し矮小化し、葉数もちょっと少なく衰退傾向が見受けられる状況ですが、老巨木としては元気なほうで立派なクスノキです。 そのクスノキに奇妙な治療がされていました。腐朽開口部と見られるところにお椀を伏せたような形にウレタンが盛られ、赤茶色に塗装だけなされています。空洞部に詰め物をするのが良いのかどうかの議論もありますが、それ以前にこの形状で詰め物をするのはダメだろうと樹木医さんなら誰でも分るような治療方法です。 集まっていた地域の人に聞きましたところ(もちろん通訳を介して)、以前ここを訪ねた日本の樹木医さんからやり方を聞いて、樹木医さんの立会いなしに地元のボランティアで処置を施したようです。 これは我々も気をつけなくてはと思わされた次第です。良かれと思っての指導であったとしても、場合によっては悪影響につながる可能性があることを考えさせられました。 [...]
コナラの独り言
わたしはコナラです。 身体はとても大きいのだけれどあまり知られていません。 サイズですかぁ? 高さは約18㍍、周囲は304㌢、そして自慢できるのが 葉張りです。四方に約28㍍拡がっています。 先月のこと、バイクに乗ったお兄さんが測ってくれました。 数年前に枝の散髪をしてくれたお兄さんだと思います。 [...]