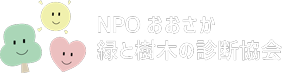樹木医アラカルト
炭焼きしてます
保水性を改善し空気を貯える空間を豊富に持った炭は土壌改良資材として利用されてきました。 また最近は炭と菌根菌を組み合わせた樹勢回復法も各地で行われています。 樹勢回復に用いる炭は備長炭に代表される白炭ではなく比較的低い温度で焼かれた黒炭や消炭が良いようです。 宅地造成のために伐採することになった広葉樹や竹をなにか利用出来ないかという要望があり、伐採材を利用した炭焼きを提案し実施しています。 里山に作られた炭焼き窯やドラム缶窯で炭を焼くのではなく、今回使用したのはステンレス鋼板で作られた無煙炭化器という装置。 “これで炭ができるの?”という思いを誰もが持ちますが、炭を焼くときに煙が発生しないため苦情がでないという優れものです。(市役所、消防署には炭を焼く旨の届け出をしています!) 点火時には少し煙が立ち上るのですが高温での燃焼のためかすぐに無煙となります。 どんどんと伐採材を投入し5時間ほどでこの装置が炭でいっぱいに。 容積にして600L程度できあがりました。 できあがった炭はかなり砕けた状態のもの。 [...]
妙国寺の手水鉢
妙国寺と言えばソテツが有名であるが、千利休寄進の瓢(ふくべ)型手水鉢も忘れてはならない。この手水鉢はこれだけをみると何の変哲もない物で、利休ゆかりの品というには余りにも面白みがない手水鉢にみえる。ただ一つ変わったところがあるとすれば、水抜き穴があいているところである。そこでその穴について考えてみた。 千利休と言えばまず思い浮かぶのは「おもてなしの心」である。その思いから考えると、「水を抜く」ではなくて「水を満たす」穴ではないか、噴泉の穴ということであれば利休らしくて面白い。 ではどうやって水を出すのか考えてみる。普通は川から懸け樋で水を引く。ここでは土居川が 近くにあるので、この水を水車で持ち上げ、懸け樋を流れた水が軒上の桶に溜まり、上からの水圧を利用して水を噴出させるという方法だろう。もちろん噴出させるには桶と手水鉢をパイプでつなぐ必要があるが、銅板を丸めて筒状にパイプを作るのは当時の技術では容易に出来たであろう。手水鉢の穴の下には左上から右下にかかる大きな溝があり、深さ7~8cm、巾4~5cm程でパイプを隠すには手ごろな大きさである。パイプを埋めて漆喰をかぶせ、その上にシダや苔等を配置すればパイプの存在はまったく判らなくなる。水の出口も水鉢の底にある為、光の屈折により見えなくなるであろう。 ところが、土居川の水では、いくら当時はきれいな水であったと言っても「おもてなしの心」には程遠いものがあり、お客様に対する気配りを考えると、井戸の水を利用するであろう。 現在のように、水道の蛇口をひねると水が出るという時代ではないので、井戸の水の利用の仕方にも工夫を凝らしたに違いない。 一番簡単な方法を考えてみた。 井戸の蓋に2か所穴をあけ、1か所には銅板のパイプを水面まで差し込み、もう1か所は足踏み式のふいごと 接続しておく。井戸の内部は漆喰や粘土で密閉してしまう。ふいごに風を送り、 圧力をかけることにより、パイプを伝って水を送り出すという方法はどうであろう。客が見えたときに、寺の小僧にでもふいごを踏ませると、その間は水が出ているという考えである。もちろん小僧や井戸は衝立で仕切られ、客の目に触れることはないし、パイプも地面に埋めて見えなくする。 当時、なんでもない石から水がわくという事は、世間の人々を非常に驚かすことであっただろうし、こういったシステムそのものを寄進した、利休という人物の奥の深さを物語るものではないだろうか。 [...]
新年明けましておめでとうございます。平成23年元旦
ついに2011年がスタートしました。 旧年中はNPOおおさか緑と樹木の診断協会に多大なるご協力とご支援を頂きましたことを お礼申し上げます。 本年も様々な取り組みや、おもしろ情報をこのブログから発信していきたいと思っております。 どうぞ、よろしくお願いいたします。
日本樹木医会を訪問しました。平成22年12月22日
我々、樹木医の本丸です。数年前に独立開業したこの場所を一回は見ておきたいと、大阪・堺大会のお礼、大阪での活動報告を兼ねての突撃レポートです。 ①東京駅からJR山手線で16分、160円。駒込駅を下車。駒込駅のホームは掘割になっており、法面がツツジの大刈り込みで緑化され、背景には桜の並木も・・・春には華やかになることでしょう! ②事務所は六義園の東側に皮一枚で立ち並んだ細長いマンションの1室です。道中には花屋さん、藍染の工房、蕎麦屋など魅力的な商店が軒を連ねています。 ③歩道幅も狭くビルは敷地いっぱいに立っていますが、街路樹のイチョウはイチョウらしく剪定されていました。土壌の組成の違いもあるでしょうが、大阪ではこうはいきません。 [...]
お城の根と防風林
■植物の逞しさ ●写真は、とあるお城の城壁。 そこには、大きな樹木がありました。 秋になると鮮やかな黄色に紅葉し、皆を楽しみにして癒してくれてました。 城壁の際に威風堂々と生育しています。 でも根が伸びていくスペースがありません。どんな風に根が伸びているかです。 [...]
高天原及葦原中国、自得照明 (古事記)
わが家のベランダから大阪の市街地が一望でき、金剛・生駒の秀峰も楽しむことができます。 真正面は、大津皇子の悲話が伝わる二上山です。晩秋から早春にかけて、北生駒の日出は物凄い。 神神しいとは正にこのことだと思います。 大津皇子の后、殉死した山辺皇女の霊魂か、伊勢神宮の斎宮を解任された大伯皇女の同母弟への熱い想いか、 メラメラと真っ赤なお天道様が昇ります。 市販の暦によりますと、東京では11月22日の小雪の日は、日出が6時23分。 12月22日の冬至の日では、日出は6時47分と書かれています。 北生駒の日出は、11月4日(木)が6時24分。 11月21日(日)は6時40分。 11月29日(月)が6時48分でした。 [...]