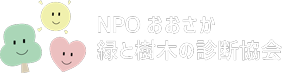樹木を切る時に使われる道具、となりますと刃物ですが、刃物には大きく分けて3種類あります。一つはナイフのように切るもの。もう一つはノコギリやヤスリのように、基本的には削るもの。そして、全く別の作用を利用するハサミ。 ハサミは切れる!という印象がとても強いのですが、実際のところカッターナイフや小刀のように鋭利ではありません。仮にハサミを手に持って、その片方の刃で木を削っても、とても小刀やナイフのような切れ味は、さっぱりありません。 しかし木の枝を切るには、やっぱりハサミが必要です。アートナイフのように極めて鋭利な刃物なら、より硬い枝がスパスパ切れるんじゃないかなと思うのですが、現実は全く反対でナイフなどではせいぜい挿し木や接木の小枝を切るのがやっとなのです。 太い枝・硬い枝を切るとなりますと、そこは剪定バサミの登場です。 剪定バサミを観察しますと、片方の刃は“刃”とはとても言えない受け刃(ほぼ、ただの角を持った金属板)になっており、片方は大きな刃となっています。 これは実に不思議です。片方は刃らしい刃がないのに、しかし大きな枝が切れる。ナイフのようなもっと鋭利な刃ものでは切れないのに・・・です。しかしこれこそが鋏の芸術的な構造、機構なのです。単にテコの原理でどうこうという訳でもありません。(テコの原理だけですとペンチやヤットコのような機構になりますが、それではもぎってちぎるような結果になります。) ハサミとは、ある一点にだけ力が集約することで、対象を切断するという素晴らしい仕組みを持った芸術品であり、いかに一点に力を余さずそらさず集約するかということについて、例えばそりやすきなどの技法が追求され、刀の技法と同様に軟鉄と鋼鉄の層構造さえも飲み込み、新たにバナジウム鋼やステンレスなどの合金までも貪欲に取り入れつつ、カッターやナイフとは全く異なり、剪断応力を引き出すため今尚進化しつづける精密機械なのです。 刃物というよりは、剪断応力の化身、それがハサミ。 極端な話、安全な鋏ということで、刃が全く切れないように刃をなめしたハサミさえあり、人体は切れなくとも、物体は切れるというハサミまであるくらいです。鋏にとって問題なのは、刃の鋭さではないわけですね。ハサミの切れ味は刃と刃がいかに厳密に点接触するかどうかによるわけで、点接触さえしていれば、刃がぼろぼろになった鋏でさえ、切断する能力を存分に発揮します。では、何故私は鋏を研ぐのか?? それは刃と受け刃が点接触するまでの過程が問題なのです。 ハサミは、仮に両刃が四角い鉄板同士でも、きちんと点接触するのであれば、切れます。 しかし点接触が起こる寸前まで、切断される対象は何が、2枚の鉄でひたすら押しつぶされていきます。ぎゅっ~と押しつぶされて、刃と刃が接触して剪断が生じます。これが良く切れる刃の場合は圧縮、押しつぶしが起きる前に対象は押し切られていくので、組織の破壊度が全く違ってくるわけです。 ちょっと実験してみましょう。 まず発生して1年以内の柿の枝を1本用意します。実験する部分で、枝の直径は細い先端で6mm、太い部分で9mmです。 次に刃がぼろぼろな剪定バサミと研いだ剪定バサミの2本を用意します。刃がぼろぼろな剪定バサミで切断する途中で切断部分に緑色の染料インクをたらします。(染料系のインクの色素は顔料系のインクより粒子が細かく、液体の浸透を確認するには適しているからです。)同じように、よく研いだ鋏で切断する部分に、赤インクをたらして、それぞれ切断します。同様に切断寸前の枝にもインクをたらします。 そして切断した断面を作るため、鋭利なアートナイフで切ります。(ハサミのようにサクっとは切れません。ナイフにはなかなか重い作業です。) そして観察しますと、刃がぼろぼろの剪定バサミで切った断面は やはりぼろぼろの鋏ですと、断面は荒れています。 一方の研いだハサミでは 緑とは断面の状態が随分違うことがわかります。ツルっとしていますね。 次に剪定バサミによる断面から2mm程度深い部分の断面の状態を観察します。 インクが内部まで染みています。 これは押しつぶされた組織が復元する時に、スポイトのようにインクを吸い上げたことによります。 研ぎたてのハサミを使った赤い方では 緑と比べて、インクが染みている部分はわずかです。 [...]